2024.11.07 学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー 【第4回 高瀬 唯先生】
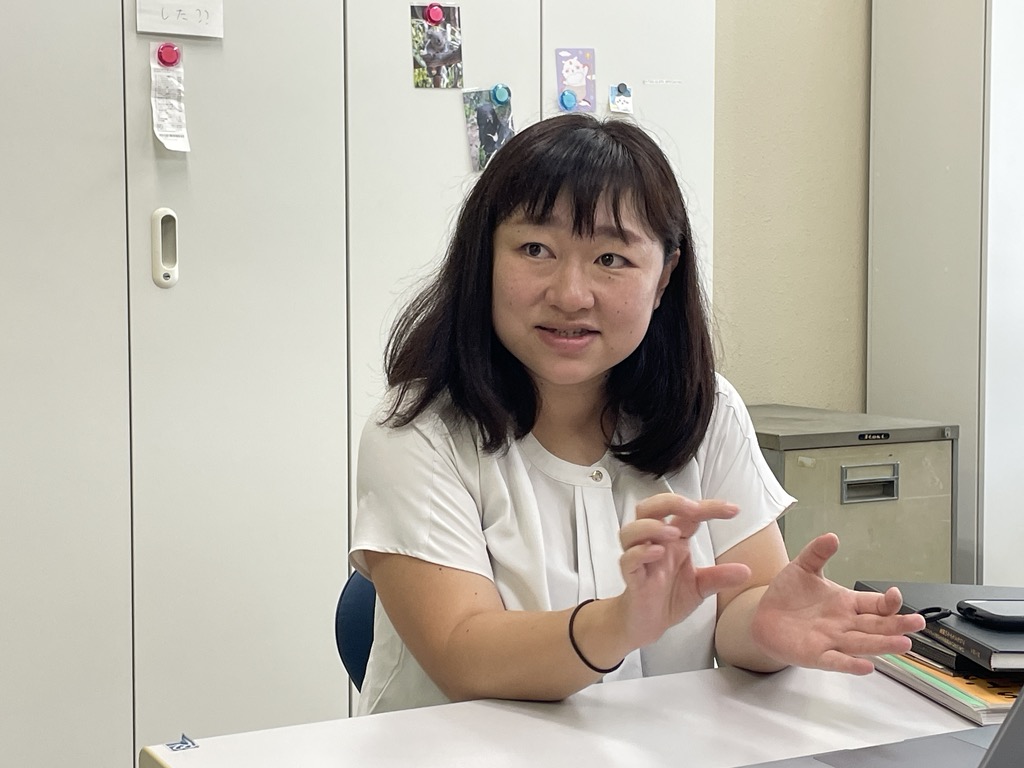
こんにちは!
茨城大学地域未来共創学環1年、学生広報アンバサダーHP運用班
最近、アメリカンコーヒーのおいしさが分かるようになった、む―さんです。
「地域未来共創学環の教員紹介」ということで、同じく学生広報アンバサダーのよしえってぃと共に、高瀬唯先生にインタビューをしてきました。
むーさん:
高瀬先生は現在ランドスケープ(景観)について研究されていますが、今の研究分野に興味を持ったきっかけは何ですか?
高瀬先生:
私が小さいころ、長期休みになると岩手の山の麓にある祖父母の家に行ってよく自然の中で遊んでいました。近くの川まで行ったり、遠くの風景を眺めたり。そのうち父の影響で始めたデジカメで写真を撮るようになりました。それから、風景や地形って面白いなって思うようになったんです。なんの変哲もない、いつも眺めている風景が、キラキラして見えて、心がワクワクしました。
むーさん:
地元の風景をみて心が躍る感覚、よくわかります。大学や学部はどのように見つけたのですか?
高瀬先生:
きっかけは出身大学の赤本です。赤本で対策をしていた時に風景計画という分野を扱っている学科を見つけて、「私のやりたかった勉強ってこれだ!」ってハッとしました。そこから志望先を決めて、無事合格しました。
むーさん:
赤本を解きながら運命の大学や学部に出会うこともあるのですね。視野を広げて大学選びをすることも大切だと思いました。
地域未来共創学環の学生は2年次から高瀬先生の『ランドスケープ整備論』を受けるのですが、具体的にどのような授業になるのでしょうか。
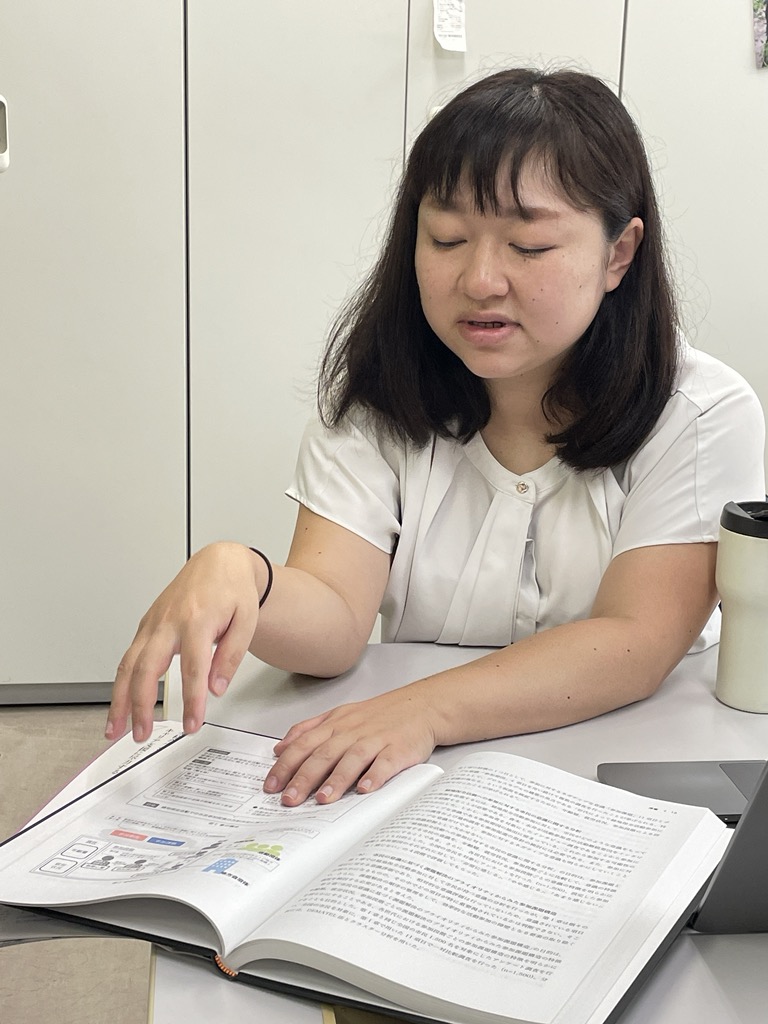
高瀬先生:
まずは皆さんに、なぜ地域未来共創学環で『ランドスケープ整備論』を学んでほしいのかを説明したのち、ランドスケープ整備の歴史を学びます。ベースを学んだ上で街中に植栽されている樹木をまとめたオリジナル樹木図鑑を作成してもらおうと思っています。ほかには整備技術や法制度なども学修していきます。
むーさん:
ランドスケープという言葉を聞いた時、地形的なことのみを学ぶのかと想像していたのですが、様々な角度から勉強していくのですね。ちなみに、高瀬先生が地域未来共創学環生に『ランドスケープ整備論』を学んでほしい理由は何ですか?
高瀬先生:
そうですね…では、地域の公園や、道路沿いの植栽の計画は誰が携わっていると思いますか?
むーさん:
その地域を管轄する役所の、植物について専門的な知識を持つ職員…でしょうか?
高瀬先生:
半分正解で半分不正解です。管轄されている自治体の職員というのはあっています。しかし、私の見解になりますが、必ずしも担当の方が専門的な知識を持っているとは限りません。そのため、適切に植栽がなされていない事例を街中で多々見かけることがあります。地域未来共創学環生の多くは地域のまちづくりに何かしらの形で関わるなど、将来そういう仕事で活躍する可能性があります。その際には、学んだことを活かして、ぜひ正しい知識と根拠をもってまちづくりをしてほしいと願っている、というのが私が地域未来共創学環生に教えたい理由です。
むーさん:
専門的な知識のある方たちが対応されているものだと思っていました!とても衝撃です。私たちが責任を持ってしっかりこの流れを変えていかないといけないですね。今お聞きしたように、高瀬先生が研究されている内容と地域未来共創学環での学びがリンクしていると思うのですが、地域未来共創学環ができると聞いた時のお気持ちを教えてください。
高瀬先生:
素直に面白そうだなと思いました。今までの学部学科ではインプットがほとんどで、大学側が実践の場をカリキュラム内に設けることはほとんどありませんでした。地域未来共創学環の教員をお願いされ、いろいろと準備をしていくうちに、素敵なカリキュラムだと思いました。これから世の中はスキル採用の時代になっていくと思っています。実践経験のない人よりも、実践経験のある人の方が企業の即戦力にもなるのではないかと思うのです。その点では、コーオプ教育が大学のカリキュラムとして組み込まれている地域未来共創学環では、短期インターンなどの「お客様」的な立場ではなく、その企業の一員として実践経験を積むことできます。そして、何より大学で学んだ内容をリンクさせて実践できるのが良いですよね。
むーさん:
私も学んだことを実践できるところに惹かれてこの学環に入りました。2年次から始まるプレコーオプ実習が楽しみです。
高瀬先生の研究室に入るまでに身に付けておいた方が良いことはありますか?
高瀬先生:
そうですね、必ずやってほしいことは一つだけです。私の講義である『ランドスケープ整備論』や『ランドスケープデザイン』を受講してください。研究する上で必要な基礎的な知識や経験を得ることができます。これを学ぶことでその後の理解がぐっと広がるのでぜひ学んでほしいです。あとは、皆さんにできるだけ色々な地域を見てきてほしいですね。
むーさん:
色々な地域を見てくる、というのはどういうことでしょうか?
高瀬先生:
色々な地域に行って、色々な風景に出会い、地元との違いに気づくことで新たな発見をするということです。私のおすすめは本屋で売られている一般的な観光雑誌に頼らず旅の計画を立てることです。多くの観光雑誌では有名な観光スポットしか載っていませんが、現地の観光協会でオススメを聞くことで知る人ぞ知るおすすめスポットを教えてもらえることもありますよ。独自でマニアックな観光ガイドを発行している地域もあります。その土地を堪能したいのであれば、観光雑誌に頼らないで旅をしてみることを圧倒的にオススメします。
むーさん:
地元で発行している観光ガイドがあるのですね!独自性があって面白いです。
高瀬先生:
私は、旅行先の地域の方々が制作したガイドマップやパンフレットを見るようにしています。地域によっては街の小道が紹介されていたりもします。

むーさん:
本日はインタビューありがとうございました。最後に高校生に向けて一言よろしくお願いします。
高瀬先生:
受験勉強頑張ってください。やりたいこと、興味があることをあきらめないで、志をなくさずに持ち続けてください。教科書だけが勉強じゃありません。外に出て、いろんなものを見て触れて出会ってみてください。茨城大学でお待ちしております。
むーさん:
本日はありがとうございました。
このインタビューを通して高瀬先生について少しは知っていただけたでしょうか?また、今回は特別に高瀬先生の研究室に所属している学生の方にもインタビューをすることができました!
以下、高瀬研究室所属の茨城大学大学院博士前期課程2年生の吉富さんとの対話です!

✨高瀬先生の印象✨
むーさん:
吉富さんにとって高瀬先生はどんな先生ですか。
吉富さん:
最初の印象は、「優しそうだな~」って印象でした。農学部には男性の先生方が多いので、それも相まって(笑)。実際に優しいんですけれど、それだけではなくて、みんなの背中を押してくれるような先生なんです。やりたいと言ったことに対して手厚くサポートしてくださったり、ご自身の経験をもとにアドバイスしてくださいます。やろうか迷っていることでも、「やってみな。絶対いい経験になるから」と後押ししてくださる先生です。
むーさん:
レールを敷いてくれるというよりは、やってみたいことへの入口まで導いてくださる先生なんですね。
✨高瀬研究室に所属して✨
吉富さん:
昔、高瀬先生に「挑戦しないと成長も何もないよ」って言われて。初めて聞いた言葉ではなかったのですが、その時やっと腑に落ちたといいますか、ハッとしたんです。私はもともとここの研究室に入るまでは、あんまりアクティブな方ではなかったんですが、ここに入って挑戦することの楽しさや大切さがわかるようになりました。今では誘われれば日本中どこへでも行きます(笑)今までやらなかったのがもったいないな~って少し後悔することもありますが、今はその分いろいろなことに挑戦しようと頑張っています。
むーさん:
それはすごい変化ですね!実際にどんな活動をされているのですか?
吉富さん:
里山保全のNPO団体のところに行って活動を見学したり、自然体験活動で子供たちのサポートを泊りがけでしたりしています。自分の勉強になりますし、子供たちの発見や疑問には驚かされます。「確かになんでだろう」と思うことや「よく気が付いたね!」と驚くこともあります。毎日が充実していて楽しいですよ。
むーさん:
とてもいきいきとお話されているので、本当に楽しそうだなと思います。今度なにかイベントなどがあればぜひお誘いください!本日はインタビューにお付き合いくださり、ありがとうございました。
この記事を読んで、「楽しそう!」「こういう先生、先輩方と学びたい」「もっと知りたい!」と思った方は、ぜひ、茨城大学の地域未来共創学環に来ていただけたら嬉しいです。
一緒に地域をより良くしましょう!あなたの創造性と意欲が必要です。
地域未来共創学環で一緒に学んでみませんか?
さて、今回も盛りだくさんな内容になってしまいましたので、この辺で締めくくりたいと思います。皆さんに会える日を心待ちにしています。
次回の教員紹介は【小原 規宏先生】です。お楽しみに~👋
記事:むーさん(学生広報アンバサダーHP運用班)
写真:よしえってぃ(学生広報アンバサダーHP運用班)
過去のインタビュー記事はこちらから☞【第1回:内田先生】
【第2回:伊藤先生】
【第3回:梅津先生】