2024.11.21 学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー 【第5回 小原 規宏先生】

教員インタビュー記事の掲載も今年度は今回が最終回となります。
学生広報アンバサダーのMOさんとISさんが小原 規宏先生にインタビューを行いました!
MO:
小原先生はどんな研究を行っているのですか。
その分野に興味を持ったきっかけなどを教えていただきたいです。
小原先生:
人文地理学の研究を行っています。地理学の研究の仕方は大きく二つに分けることができます。
一つ目は、一つの地域で色々なテーマを探す方法です。もう一つは、テーマを決めてから多くの地域で比較する方法です。
主に、前者の方法で研究に取り組んできました。
さいたま市出身で、子供のころに遊び場として里山を利用していました。 その後、首都圏の都市化が進み、何となくその変化が気になって地理学を専攻したいと考えました。そして、進学した大学の教員と出会い、里山の調査に関心をもち、自分の感じた里山の楽しさについて知りたいと思ったのがきっかけです。海外の里山にも興味があり、特にドイツの事例について研究していました。茨城に来てからは、県央や県北を中心に農山村の活性化に取り組んできました。茨城は農業が盛んですよね。平地が広がっていて大量生産が可能であり、東京から近い交通の便の良さが関係しています。しかし、生産主義的な姿勢を見直すことは重要です。私は、観光をツールの一つとして地域活性化のお手伝いをしてきました。コロナ禍を経て大学時代の教員と再会したのをきっかけに、原点回帰で里山をもう一度研究しようと思いました。栃木県の北部に広がる里山の那須野が原をフィールドに研究テーマを探し始め、今は新しいエネルギー事業や若い移住者による新しい農業などに関心を持っています。調査していて面白いのが、移住者たちが地域資源に今日的な新たな価値を見出すことで新しいライフスタイルを創出したり、新商品を開発していることです。例えば、地域の農業用水を利用した小水力発電の導入によるエネルギー自給への取組みです。扇状地の扇央部に位置するため長らく水を利用しづらかった那須野が原では、明治期の開拓で農業用水を利用できるようになったことで地域が発展していきました。その農業用水をエネルギーの自給という今日的な観点から利用しようという試みです。
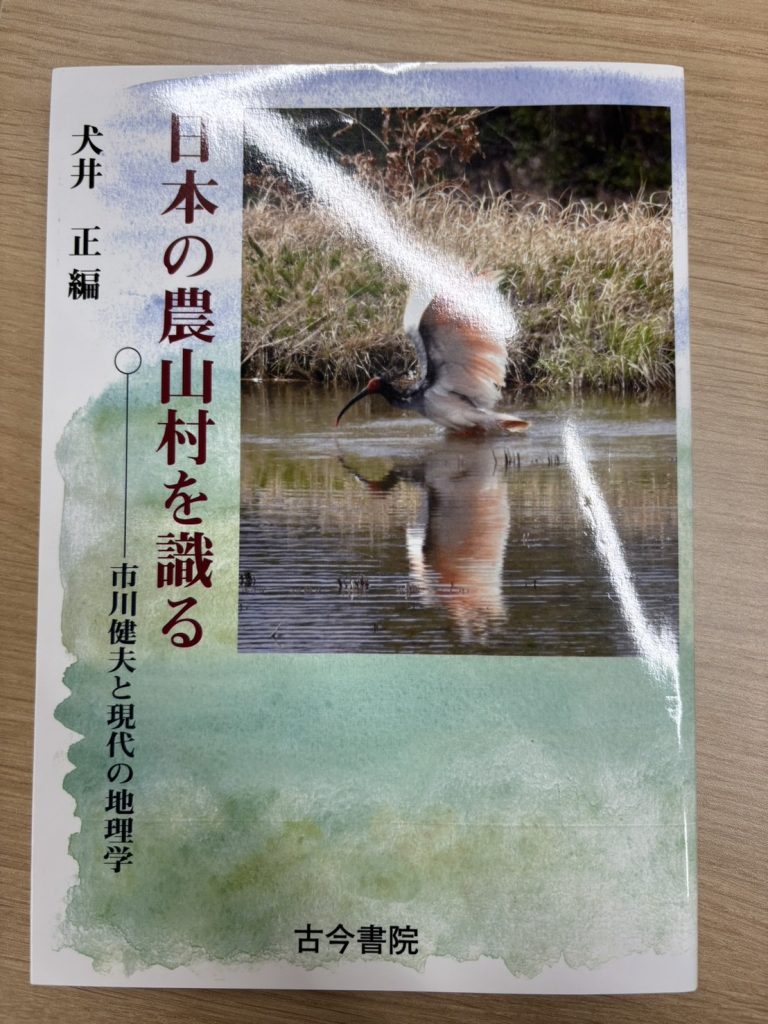
MO:
新たな価値を地域の産業に創りだしていくというのは、地域未来共創学環の目指している目標と近いように感じます。先生の研究分野に学環の学生はどのように関わっていけると思いますか。
小原先生:
人文地理学は長らく人が地域の環境にどのように適応し、地域を発展させてきたのかを明らかにしてきました。学環の学生が地域の環境に気を配り、どのようにビジネスを起こせるのか考えています。起業や新しい仕事を創りだすことは難しいですが、コーオプ実習を通して実践を積むことで何ができるのか楽しみにしています。
MO:
小原先生のゼミについて教えてください。
小原先生:
グローバルに考え、ローカルに活動することを心がけています。笠間市の市民グループと交流していて、学生には市民たちがどのように地域活性化に取組んでいるのかを現場で見てもらいながらゼミとして地域活性化の取組みに参加してきました。人との関わりを密に、フィールドワークで地域に入り地域の人とのつながりを大事にしています。

IS:
小原先生は人文地理学の授業を担当されていますが、どのような授業を行っているのですか。
小原先生:
私の授業では、地域、場所、景観に焦点を当てています。授業では、3つのステップを踏むことで学生に地図や景観を読めるようになっていただきたいです。まず1つめのステップは、地図や景観がもつ大量の情報を読み取り、地域や場所そのものを知るということです。次に、地図や景観の特徴からその地域がどのような過程で作られてきたのかを読み解いていきます。これには、学生の皆さんには地域を診断するお医者さんになってもらいたいという思いがあります。様々な要素を分析しながら、統計の手法も取り入れています。そして最後は、地図を読み解いて分かったことが地域活性化やむらおこしにおいてどのように活かせるかを考えるというステップになります。私の授業は、学生がこれらの3つのステップを実践できるような構成になっています。
IS:
とても興味深い授業だと感じました。最後に、受験生へのメッセージをお願いします。
小原先生:
大学で授業を行っていると、地域を見るという観点で学生の視野が狭いように感じます。単純な好みからテーマを設定する学生が多く、その地域の背景や課題をあまり捉えられていないことがよくあります。そのため、受験生の皆さんには、色々なものに興味を持つこと、自分が関心のある地域以外にも視野を広げること、地域をたくさん見ることをお勧めします。広い視野で様々な地域を見ていくことがいつか自分の糧になると思います。色々な授業を受け、多くの先生と関わることで、いつか自分がやりたいことはこれだと思えるものに出会えると思います。最初は範囲を限定することなく広い視野を持ち、その中で関心を持ったものを深く学んでいくと良いのではないでしょうか。
MO、IS: 小原先生、ありがとうございました。
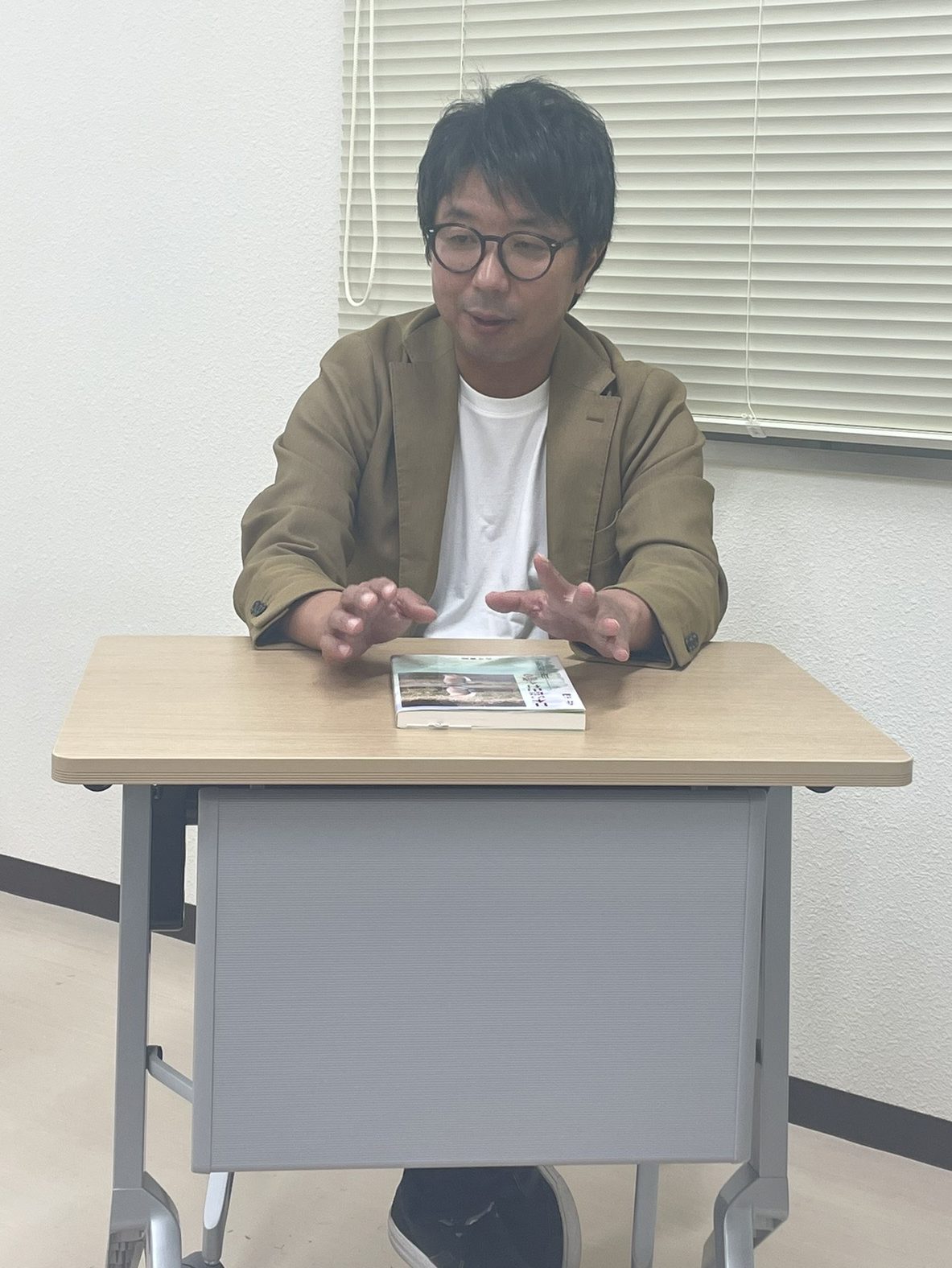
全5回にわたってお届けしてきました「学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー」は
いかがだったでしょうか?
今年度は今回が最終回になりますが、地域未来共創学環には、まだまだ興味深い研究を行っている先生方がいらっしゃいます。
次はあなたが地域未来共創学環の教員にインタビュー🎤を行ってみませんか?
みなさんのご入学を楽しみにお待ちしています✨頑張れ!受験生🌸